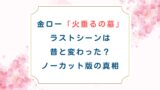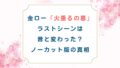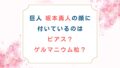『火垂るの墓』における清太と節子の家の「7000円の貯金」は、物語の重要な要素ですよね。
「清太は7000円の貯金をいったい何に使ったの?」
「7000円は今の価値だとどのくらいになる?」
「大金があったのにどうして清太たちは飢えてしまったの?」
など、気になっている方も多いですよね。
そこで今回は以下の内容で記事をまとめたので、ぜひ最後までご覧ください!
▶【火垂るの墓】貯金7000円の使い道
▶【火垂るの墓】7000円の現在の価値
▶【火垂るの墓】大金があったのに飢えた理由
【火垂るの墓】貯金7000円の使い道

さっそく、「火垂るの墓」で清太が貯金7000円をどのように使っていったのかについて確認していきましょう。
清太が使った7000円の具体的な使い道を、劇中描写から見ていきます。
お金の多くは、闇市や小売で生活物資の調達に消費されました。
このように、最初は贅沢に物をたくさん買っていましたが、品不足や価格の高騰ですぐに使い切ってしまい徐々に現金の価値が減っていったことがわかります。
戦時下で物資が極度に不足し、闇市取引は正規価格の10倍以上になることもあり一般的な価値観は通用しませんでした。
【火垂るの墓】7000円の現在の価値

当時(昭和20年頃)の7000円は、庶民の年間給与の何十倍にもあたる大金です。
定説では、現代価値に換算すれば3,000万円~5,000万円程度が目安とされます。
・兄妹の経済的背景がいかに裕福だったのかを示している
・しかし戦時下の社会ではそのお金すら、命を守る力にはなりにくい現実が描かれている
戦時中は物と交換する闇市が主流になり現金よりも着物や貴金属などの物品の方が価値が高く、戦争状況下ではお金が役に立たない理不尽さや人間社会の脆さが作品のテーマの一つになっています。
当時の物価はどのくらい?
『火垂るの墓』の舞台である昭和20年(1945年)当時の代表的な物価をまとめました。
| 品目 | 価格(1945年頃) | 備考 |
|---|---|---|
| 米1kg | 約2円 | 配給制で自由購入は困難 |
| 米1斗(約15kg) | 約3.3円 | 闇市ではこの約10~20倍 |
| 庶民の家賃(1か月) | 10〜15円 | 都市部の長屋など |
| 公務員初任給 | 約75円 | 大卒のケース |
| 小学校教師の月給 | 約80〜100円 | 地域差あり |
| 一般住宅 | 約1,500円 | 都内の戸建て住宅等 |
| 新聞1ヶ月分 | 約1円 | |
| 東京−大阪間鉄道賃 | 約6.35円 | 当時の正規価格 |

こうして見てみると、清太の家がいかに裕福だったのかがよくわかるね。
ただし、実際の戦時下では物資不足と闇市価格高騰により、現金の価値は大きく下がり「お金で物が買えない」状況が続いていました。
闇市だと米1斗(約15kg)が30~60円にもなるなど、正規価格の10倍以上に跳ね上がることも珍しくありませんでした。
【火垂るの墓】大金があったのに飢えた理由

『火垂るの墓』で清太と節子が「大金(7000円)」を持っていたにもかかわらず飢えてしまった理由は、戦時下という異常な社会状況と複数の要因が絡み合った結果からです。
- 物資不足と流通崩壊
戦争で日本全体が深刻な物資不足。
生活必需品や食料の配給は極端に限られ、正規ルートではそもそも「買える物」がほとんどなかった。 - 闇市価格の高騰
闇市で食糧や日用品を買おうとすると、正規価格の10~20倍といった「非常識な物価」で取引されていた。
大量の現金があってもすぐに底をついてしまう。 - 子供だけの生活の限界
清太と節子は幼い兄妹。
社会的な情報収集や大人の助けを得て有利に立ち回る力が不足し、円滑な物資調達や交渉ができなかった。 - 社会的信用の喪失・孤立
親戚宅を自ら出たことで、頼れる大人や親族の庇護=「社会的信用」を失った。
現金があっても大人社会の中で無力になり、助けてくれる人もいなくなった。 - 戦争による経済体制の崩壊
日本全体がインフレや経済崩壊の只中にあり「お金の価値」「社会インフラ」が激しく機能不全。
現金さえあれば何でも解決できる平時の常識が通用しなかった。

結局清太が世間知らずだったとは思うけど、当時の中学生が異常な状況下でうまく生きていくのは相当難しいよね。
「大金があれば生き残る」という方程式が通用しないのが戦争の現実です。
「物と交換する力」や「社会的な助け」がないと、どんな金持ちでも飢えに直面するという戦争の非人間的な悲劇がリアルに描かれている作品です。
まとめ
今回は『[火垂るの墓]7000円は何に使った?今の価値はいくらになる?』について紹介しました。
▶【火垂るの墓】貯金7000円の使い道
・節子と自分のための食料・日用品の買い物
・親戚宅を出て独立した暮らしに必要な炊事用具・生活用品
・節子の薬や栄養補助食品
・短期間の家賃・住居費
▶【火垂るの墓】7000円の現在の価値
『火垂るの墓』で語られる「7000円」の現在の価値は、さまざまな推定がありますがおおよそ数百万円~5,000万円前後とも考えられています。
▶【火垂るの墓】大金があったのに飢えた理由
1.物資不足と流通崩壊
2.闇市価格の高騰
3.子供だけの生活の限界
4.社会的信用の喪失・孤立
5.戦争による経済体制の崩壊
最後までご覧いただきありがとうございました!
![[火垂るの墓]7000円は何に使った?今の価値はいくらになる?](https://07kurata27.com/wp-content/uploads/2025/08/パステル-ブロブ-基本-シンプル-プレゼンテーション-2025-08-16T060710.912-768x432.jpg)